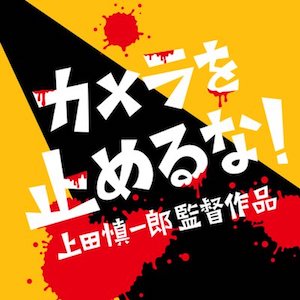M-1グランプリ2019に見る現代漫才の最適解、ミルクボーイとぺこぱ
2019年のM-1グランプリが終わった。ボジョレーヌーボーのごとく毎年書いている気がするが、今年のM-1は近年稀に見る出来栄えだった。
中でも最終決戦に進出した3組、ミルクボーイ、かまいたち、ぺこぱは素晴らしかった。個人的にはかまいたちのネタが好きだったが、神がかっていたミルクボーイの優勝に文句はない。
見ているときは、ああ、おもしろいなあ、と笑っていただけだったが、見終わってしばらくして、ぺこぱは「世間」が求める漫才の最適解を発見したのではないかと思った。それについて書きたい。
新ネタ発表会に回帰したM-1グランプリ2019
2015年の復活以降、「新しさ」より「うまさ」を競うコンテストになったかに見えた第2期M-1グランプリ。
だが、2019年は、「新しさ」を重視する第1期(2001年〜2010年)、ナイツ・塙が言う「新ネタ発表会」だったころに戻ったような感じだった。
僕にとって、M-1はやはり新ネタ発表会です。 言い訳 Q72
決勝に残った10組のうち7組が初進出。決勝経験者はかまいたちと見取り図、敗者復活戦から上がった和牛だけ。
M-1運営サイドが意図的にそうしたのか、単純に準決勝でウケてた組を選んだらそうなったのかは分からないが、結果的にはこの変化は大成功だったのではないか。
現代漫才の最適解
そんな「新ネタ発表会」に回帰した2019年のM-1グランプリで輝いたのが、最終決戦に残ったミルクボーイとぺこぱだ。
見ているときは、ああ、おもしろいなあ、と笑っていただけだったが、見終わってしばらくして、特にぺこぱは「世間」が求める漫才の最適解を発見したのではないかと思った。
続くツッコミ主体漫才
2018年の感想に書いたように、近代漫才の特徴は、
- ツッコミ主体
- 手数の多さ
にある。近代漫才の覇者が2018年のチャンピオン、霜降り明星である。
「手数の多さ」を重視していた(ように見えた)コンビはインディアンスぐらいだったが、2019年も「ツッコミ主体」の流れは続いている。かまいたちはちょっと違うが、ミルクボーイもぺこぱもボケ自体は大したことは言ってない「ツッコミ主体」の漫才だった。
なぜツッコミが重視されるようになったかはいろんな考え方があるが、「分かりやすさ」と「安心感」は理由に挙げられるだろう。
ツッコミは観客側の人間であり、ある意味「異常者」であるボケの通訳として機能する。強力なボケで押し切る漫才よりもしっかりとツッコんでくれる漫才のほうが、分かりやすく、安心感がある。
「分かりやすさ」と「安心感」は、漫才に限らず、様々な場面で現代の日本人が求めているものではないか。
否定を許さない世間のムード
ツッコミといえば、今大会で話題になったのが、松本人志のニューヨークに対する「怒っているツッコミのほうが好き」というコメント。
僕の好みなんでしょうけど、最近ツッコミの人って、結構、笑いながら楽しんでる感じが(して)、あまり好きじゃないんですよ。
...
僕はツッコミが怒っているほうが好きなんですよ。
確かに最近のツッコミはあまり怒らない。
その理由は、(あえて曖昧な言葉を使うならば)「世間」が怒りツッコミを求めていないからだろう。
ツッコミとは訂正であり否定である。そこに怒りが加わると、否定の度合い・強さは一気に高まる。「世間」は否定を求めていない。
若い芸人たちはそんな「世間」のムードを敏感に感じ取っている。
最近だとティモンディの高岸、ちょっと前だとANZEN漫才のみやぞんのように、「世間」に愛されるのは、なにも否定せずにニコニコしている楽しそうな人たちだ。仲良しコンビが人気なのも「世間」のそんなムードを反映しているといえる。
蛇足ながら書いておくと、否定を許さない「世間」が優しい世界なのかというとそうでもない。否定を避ける一方で、ひとたび「この人は否定してもいいんだ」という烙印が押されると苛烈なまでに否定するのが現代の「世間」でもある。
さらに蛇足を加えると、このようなムードは日本だけのものでもない。世界中で、否定してもいい口実のために有名人の過去の発言が引っ張り出されている。
--
このような、分かりやすく安心感のあるツッコミ主体の漫才を求める一方で(ツッコミの本質である)否定はしてほしくない、という「世間」からの難問に対する解答が、ミルクボーイとぺこぱのネタだった。
否定をあるあるネタと昭和の香りで包んだ、ミルクボーイ・内海崇
ミルクボーイのネタは内容だけ見ればコーンフレークと最中を否定するものだったといえなくもないが、全体としては否定的な印象はあまり受けない。
内海のツッコミは、練りに練られたワードや着眼点は見事だったとはいえ比較的オーソドックスなものだった。大雑把に分ければあるあるネタだといえる。
観客の共感を呼ぶあるあるネタは、否定をマイルドにするのに一役買っていた。
それだけではない。
同じ題材・構成だったとしても、もし内海が「コーンフレークを晩飯で食うアホがどこにおんねん!」と青筋を立ててツッコんでいたらここまで受け入れられなかっただろうし、一言一句まったく同じ台本だったとしても他のコンビがやっていたらここまで爆発しなかっただろう。
全体のトーンを決定づけていたのは、昭和のオッサンのような内海のキャラクターだったと思う。人の良さそうな角刈りとつぶらな瞳が平和な雰囲気を醸し出していた。
ミルクボーイに対して今大会の最高得点99点をつけたナイツ・塙はこうコメントした。
誰がやってもおもしろいネタ、プラス、この人たちがやったら一番面白いっていうのがベストのネタだと思うんですよ。
...
人の力と言葉の力とセンスが凝縮してたので、ほぼ100点に近い99点です。
まさしくその通り。
行ったり来たりする大枠の構造の分かりやすさや、そもそもオカンの言うことをまったく疑わない優しさも良かった。「お前のオカン何言っとんねん」みたいなセリフが一つでもあったらまったく別の印象になっていたに違いない。
コーンフレークと最中というネタのチョイスも正解だった。毒が強めのサイゼリヤのネタは(個人的には好きだが)M-1には向いていないだろう。
誰も傷つけない、何も否定しない、ぺこぱ・松陰寺太勇
ミルクボーイが人の力と言葉の力とセンスを凝縮させるという正攻法で万人に受け入れられる漫才を作り上げたのに対して、コロンブスの卵的な発想で「否定しないツッコミ主体漫才」という難題を解いたのがぺこぱだ。
ぺこぱのツッコミは革新的だった。発明といってもいい。
松本人志が「ノリツッコまないボケ」と評したように、厳密にはぺこぱ・松陰寺太勇のツッコミはツッコミではない。みんなが必死に探し求めていたツッコミはもはやツッコミではなくボケだったというのはまるで現代の寓話のようだ。
アイデアの勝利。
「その手があったか!」と悔しがっている芸人がたくさんいるのではないか。
中川家・礼二が言っていたように明らかに定まっていないシュウペイのキャラクターなど、荒削りではあったが、誰も傷つけず何も否定しない(それどころか肯定する)ぺこぱの漫才は、「世間」が求めるものだった。
着物を着てローラーシューズを履いていた頃からよく仕上げたと思う。すごい。
その先へ
ぺこぱの漫才は「世間」が求める漫才の最適解だったが、もちろんそれが唯一の解ではない。
2017年のジャルジャル・福徳の言葉
ジャルジャルの福徳は2017年のM-1グランプリを振り返ってこんなことを言っていた。
(ピンポンパンゲームは)誰もが笑うネタやろなと思ってたんですよ。
誰も傷つけてない笑い、まさにこれだ!
誰も傷つけず笑いを取った、誰もバカにしてない、自分ら二人だけで完結した、めちゃくちゃ平和なネタ、老若男女にウケる、(そんなネタをやったのに)点数振るわへん、泣きそー! AbemaTV エゴサーチTV 2017年12月8日
注目すべきは、2017年の時点で「誰も傷つけない笑い」でなければM-1では勝てないと認識していたということだ。
「誰も傷つけない笑い」に対するジャルジャルの答えが『ピンポンパンゲーム』であり、2018年の『国名分けっこ』だった。ツッコミが主体のほうが分かりやすいとかいう次元ではなく、そもそもボケとかツッコミとかいう概念を超越した、何が何だかよく分からないけどおもしろい、そんなネタだった。
その手があったか、ではなく、何なんだこれは、と思わせるようなネタ。それも一つの答えだろう。
一番おもしろかった天竺鼠・川原
敗者復活戦と決勝を通して今回の大会で自分が一番おもしろかった瞬間は天竺鼠のツカミ(「場所取っといたで」)だった。
ただ単に天竺鼠が好きなだけだろ、と言われれば、はいそうです、と答えるしかないのだが、強力なボケがあればそれだけでいいんだ、という気持ちになった。
「ツッコミ主体」「ツッコミが華」の時代だからこそ、そろそろボケの復権を期待してしまう。
ナイツ・塙も著書『言い訳』でこう語っている。
番組は本当にサッカーチームに似ています。役割分担が大事なのです。
...
天竺鼠の川原(克己)君が出現したときは、大器の予感がしました。でも、いまいち点が取れずに悩んでいるようです。誰もパスを出してくれないのです。
...
今の時代、「ボケ専門」は空気の読めない芸人みたいな扱われ方をしてしまうことが多いんです。
こんな時代だからこそ、漫才界の常識を打ち破る、スケールの大きなボケに出てきてほしいんですよね。 言い訳 Q90
「誰も傷つけない・否定しない笑い」が求められるのは当分続くと思うが、「ツッコミ主体」の流れはボケのスーパースターが登場すれば変わると思う。
マヂカルラブリー・野田クリスタルのような狂気を秘めた目をしたボケがもっと登場してほしい。マヂカルラブリーが老若男女に愛される姿は想像できないけど。
いずれにせよ、敗者復活戦でもラストイヤーの天竺鼠の漫才を見れたのは嬉しかった。お疲れさま瀬下。
そのほかの感想
そのほか、M-1グランプリ2019を見て思ったことをいくつか書いておきたい。
もっと評価されてほしかったオズワルド
オズワルドはおもしろかった。POISON GIRL BANDを彷彿とさせるスタイルが最高だった。ミルクボーイの大爆発の後でよく自分たちの漫才をやりきったと思う。
ナイツ・塙と立川志らくの評価が低かったのはなぜなのか分からない。好きそうな感じなのに。特に塙の寸評は聞きたかった。
「細稲垣」も俺はアリだったと思うよ!
ネタが飛んでいたとは思えなかったインディアンス
準決勝の順位は一位で優勝候補だったインディアンスは残念ながら不発に終わった。
リアルタイムで見ていたときはなんか調子悪そうだなという印象だったが、決勝後の打ち上げ配信で田淵がネタが飛んでいたと告白していてビックリした。録画を見返してみても、不自然な部分はあるものの頭が真っ白になっていたとはとても思えなかった。
ネタが飛んでいてあそこまで持っていったのはすごい。漫才師の底力を見た。来年は自分たちの漫才をやり切ってリベンジしてほしい。
紹介VTRは控えめにしてほしい
素晴らしい番組を作ってくれているスタッフの方に文句を言うようで申し訳ないが、ネタ前のコンビの紹介VTRが語りすぎだと思う。
これからネタを見るのに、どんなコンビなのかを説明する意味があるのだろうか。どっちがボケでどっちがツッコミかも知りたくない。
さいごに
ということで、今回のM-1グランプリも非常におもしろかった。
イタいお笑いファンとしてはついつい語りたくなってしまう魅力がM-1グランプリにはある。
来年も楽しみです。